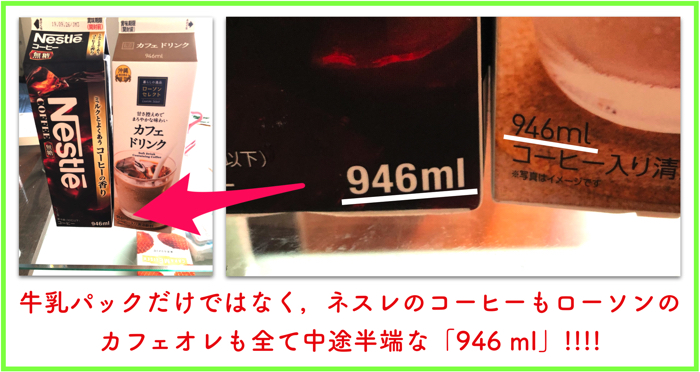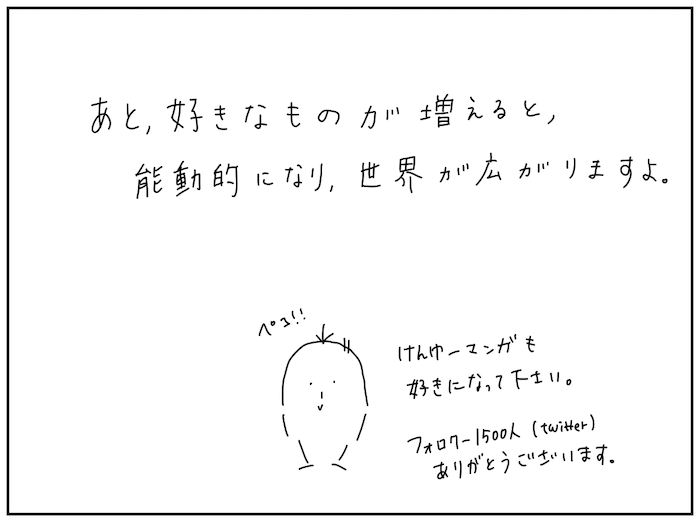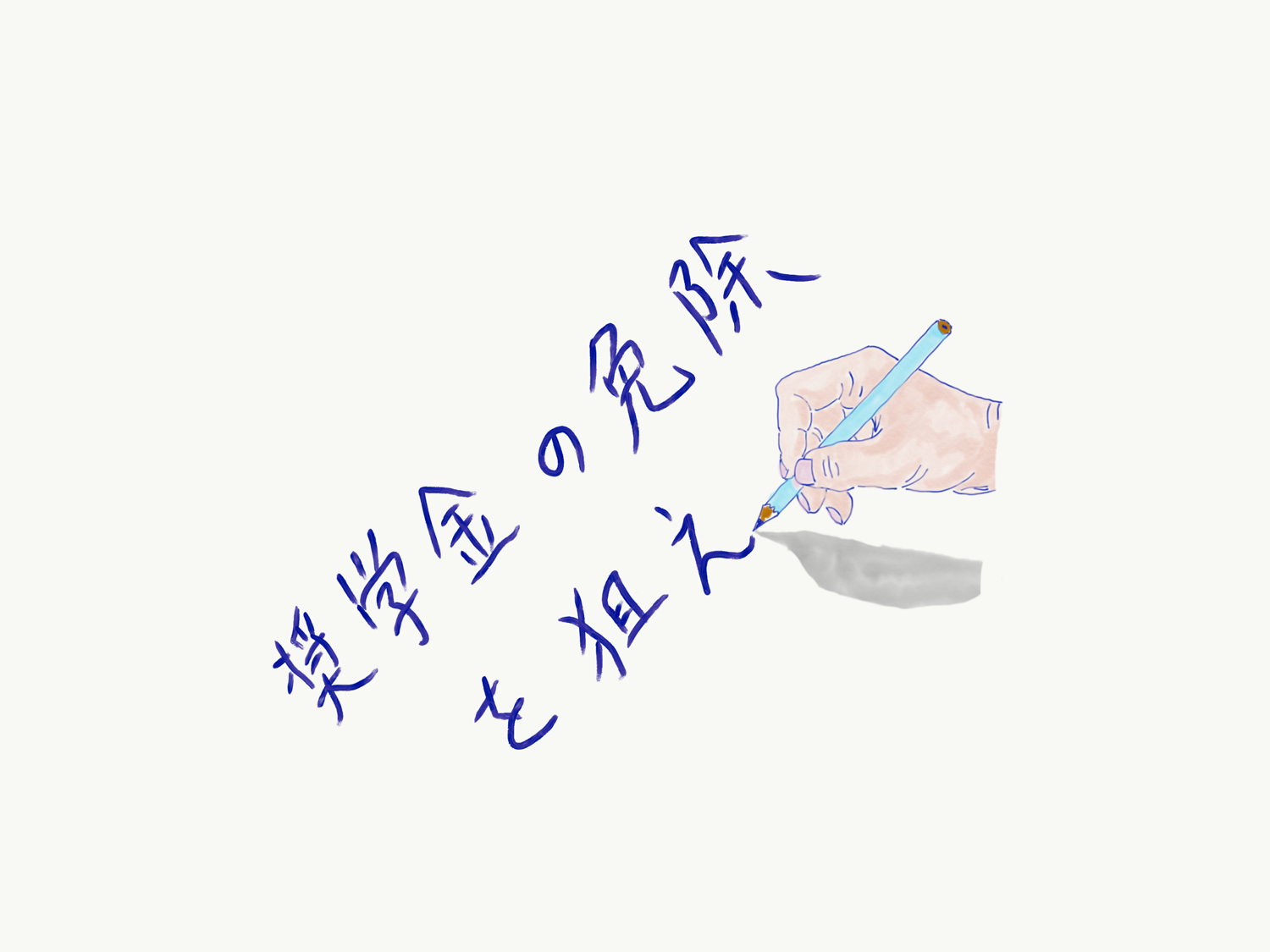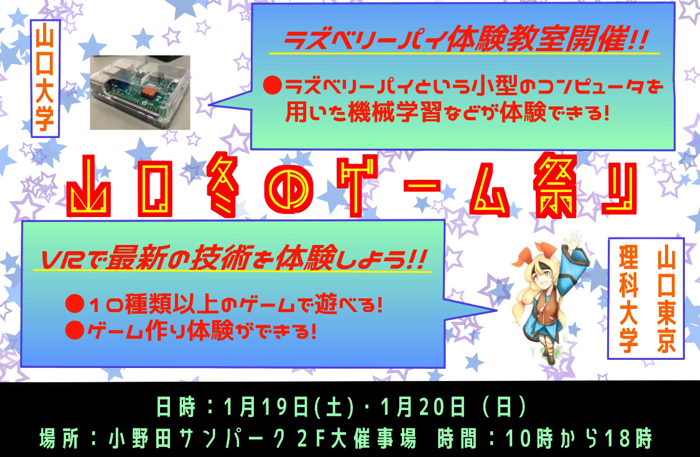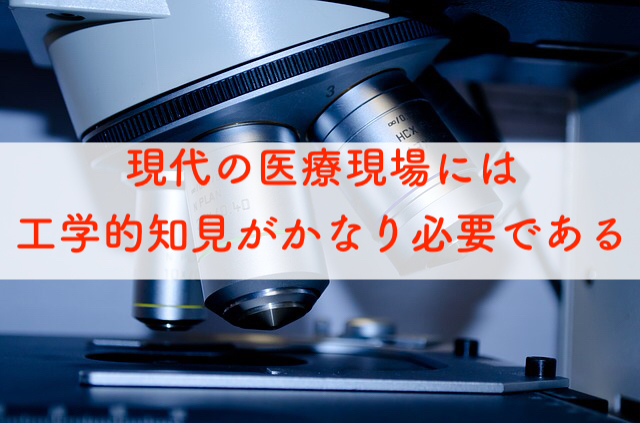
- 工学と医学の勉強をしている学生
- 先端医療機器に興味ある方
- 山口大学の修士課程の学生の方
こんにちは.けんゆー(@kenyu0501_)です.
今日は,おいらみたいな工学と医学の狭間で研究をしている学生さんに向けたオススメ記事を書きます.
おいら修士課程では,山大の医学系研究科を修了しているのですが,その中でも一番面白かった講義は「先端医療機器特論」という講義ですね.
どんな講義かというと,医療機器開発をしているメーカーさん達の講演を毎週聞きまくるという講義です.
正直,勉強形式の講義って,つまんないんですよね.
(教える側も上手ではないですし,自分で本読んだようが早いです.)
学生だからこそ得られる価値というのは,こういう講義にこそ集約されていると思います.
(メーカさんとの繋がりでしょうか)
この記事では,講義を実際に受けてみて,おいらなりのちょっとした解釈を書いていきます.
先端医療機器特論とは
簡単にいうと,各医療機器メーカーの得意としている医療用デバイスや最新の技術などを紹介していただく講義です.
(レポート提出はあったような..)
覚えている範囲(おいらが受講したH 27年度後期)だとこんな感じです.
- 芝メディカルシステムズ
- GEヘルスケアジャパン
- オリンパス
- 島津製作所
- 日立メディコ
- アークレイ
- ニプロ
などなど
他はちょっと忘れてしまいましたが,,,
毎週あるので,ざっと10社以上の話を聞くことができます.
(教員の先生のツテで呼ばれていると思いますが,豪華です)
覚えている限りで概要
内側の話はブログに書けないので,ざっくりと...
芝メディカルシステムズやGEヘルスケアジャパンは主に画像支援装置であるCTやMRIの技術,またオリンパスや島津製作所,日立メディコは,内視鏡手術,PET(陽電子放射断層撮像),放射線治療などの独自の技術の紹介がされたと思います.
他にも自己血清測定器を扱うアークレイやダイアライザを扱うニプロなど,その業界で活躍している有名な企業さんのお話を聞けます.
おいらが思うこれら企業の共通している最大の武器というのは,診断が非侵襲で行える機器を開発されているという事です.
患者の体を第一に考えている企業さん達でした.
診断によって人体の持つ機能や形態を壊す恐れが小さいという事は非常に患者にとってメリットですよね.
それと同時に高精度な診断評価を可能とする技術が進むと,病気の早期発見が可能であり,検査前後の入院数が従来と比べて少なく,医療スタッフ側にとっても大きなメリットだったりします.
そういった現場にとって大事なことや,時代の医療ニーズを聞くことができたのでためになりました.
以下は,講義を受けて,おいらが思ったことをつらつらと書きます.
医療において工学的観点からできる事とは?
非侵襲的に診断をする技術の開発においては,医学の知識だけではなく,工学系の知識も非常に重要だと思います.
これは,いろんなお医者さんとお話ししても,みなさんそう言われます.
(持ち上げられているわけではなく,事実そうです.)
実は,病院にある診断装置は機械工学技術の集合体だったりするので,工学的な知見は有用だったりします.
例をあげると,あるメーカさんはX線の挙動をモデル化しモンテカルロ法を取り入れたシミュレーションをされていたし,
内視鏡検査では生体部位の光の吸収率の違いを利用し,コントラストをつけることによって腸内ポリープの有無を確認していたりします.
いかにも機械工学科が好きそうな,,,
現代医療は,他分野の集合ですが,機械工学で担う部分って割と多いんですよね.
今後の医療を支えるためには機械工学を専門とした人が大きな影響を与える位置づけになっていることを感じ取れてちょっと勇気が出ます.
(言い過ぎかな,,,)
日本医療の問題点をちょっと考える
他の先進国と比較して,日本医療の問題点を考えたときに,病棟の医療密度が極端に低い事(病棟当たりの医師や看護師が少なく,入院期間が長い)が挙げらると思います.
詳しくは,国際医療福祉大学大学院の高橋泰教授の「今後どのように医療提供体制の再編を進めていくべきか」をご覧いただけたらと思います.
上の本文中に,日米間の同規模の病院を仮定した時の百床当たりの医師数と看護師数の格差をイラストで示しているところがあります.
それを見ると,アメリカは日本に比べ約4~5倍の医師や看護士がいることになり,短期的な集中治療が提供できる事を示しているようです.
これは日本の少子高齢化(若者の減少)に加え,昨今の理系離れによる結果だとも思いますが,ここに,医療機器が発達するチャンスもあると思います.
病院の待ち時間が長いのも?
病棟の医療密度が極端に低い事は,どういうことに繋がるかというと,,,,
例えば,昨今は,病院の待ち時間が長いからどうにかならないのか議論が盛んでした.
ホリエモンが「総合病院の待ち時間が長すぎる」とか言ってブチ切れてたのもそうだけど、公共サービスというのは金持ちを優遇しないので金持ちにとっては相対的に自分の価値が下がってるような感覚を与えてしまうんだよね。金持ちは基本的にバカで傲慢なので、その「平等」に耐えられない。
— 小山晃弘 (@wakari_te) January 27, 2019
この件に関しては,おいらはとても否定的で,金持ちは傲慢とかそういうものではなくて,やっぱり病院の待ち時間って長い事には原因があると思うのですよね.
その原因を見つけて,技術的に解決できればそれに越したことはないわけですよね.
(別にシステム的でも良いですが)
現場においてある医療機器の診断制度が向上すると,何度も通院する必要も無くなるわけで,この辺も大事なのかな,,と思っていたります.
他分野のコミュニケーションは大事
医学と工学というのは,医療を支える上で密接に繋がってないといけないと考えるので,こういった現代に蔓延る(はびこる)問題を解決するためには,やっぱりコミュニケーションって大事なんですよね.
現場で機器を扱う医療スタッフ側が,より使いやすいような装置の開発をする際にも,技術者との交流は必須です.
コミュニケーションだけではなく,実際に開発や設計,臨床試験までを医師を含めた形でそれぞれ一緒に行っていくのも一つの方法だと思います.
(すでにされている例も聞きます)
講義でどっかのメーカさんが漏らしてましたけど,日本医療機器メーカーは,内視鏡や超音波,CT,MRIなどの画像診断機器はかなり得意だが,病院での新機種導入の際には,外国製を希望する病院が多いらしいですね.
海外製品の方が医者にとって取り扱いが安易であるためであるとかどうとか.
この辺は,村惣一郎さんの「日本の医療機器の現状課題と改革へ向けての提言」を読むと面白いかもしれません.
こういうことを考えさてくれるオススメの講義なのでした.